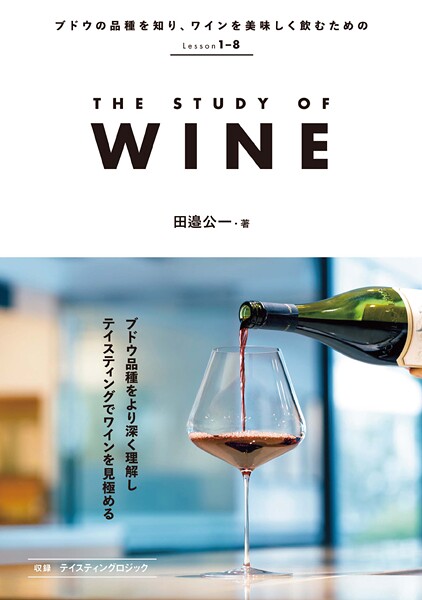ワインに水を加えることの意味
この説は、少なくとも近代(19世紀末〜20世紀初頭)に、近代衛生の価値観で過去を説明する語り口として形を整えた、と考えるのが自然です。
具体的に、英語圏の入門的な説明でよく見かける言い回しに近い形は、1913年の L. F. Salzmann(中世イングランドの産業史)に見えます。そこでは、麦芽酒(ale)が「茶やコーヒーのような近代の飲み物だけでなく、水の代わりにもなった」と述べられ、さらに13世紀の逸話として「極端に貧しい修道士が、酸っぱすぎるエールを飲み、むしろ水を飲みたがった」という話が引かれます。
ここで重要なのは、Salzmann 自身が扱っているのは主にイングランドの麦芽酒文化であり、これが後世の紹介で「中世ヨーロッパ一般」や「ワイン」にまで拡張されやすい、という点です。
同じ時期(20世紀初頭)には、醸造史・産業史の文脈で「昔は水が汚かった → だから発酵飲料」という筋書きを強める記述が増えます。同時期の醸造史・産業史の文脈では、「昔は水が汚かった → だから発酵飲料」という筋書きを補強するために、水事情を強い言葉で描写する記述が目立つようになります。
こうした“衛生の進歩を強調する近代の語り”が、後に「中世=水が飲めない」という印象を作り、地域差や状況差をならしてしまった、という流れが想定できます。
さらにもう一つ、中世の飲酒歌・討論詩には、ワイン(酒)を称え水を呪う表現が繰り返し現れます(例:中世ラテン語の飲酒歌や「ワイン対水」の討論詩で、水を貶す定型表現が反復されることがあります)。
これは本来は文学的な誇張・遊戯(薄め酒批判など)ですが、近代の読者が文脈を外して読むと、「当時は水が病気のもとだった」という“事実説明”に見えてしまい、上の衛生ストーリーと結びついて説の説得力を増す――という構造が生まれやすかった、と整理できます。
水は本来、幼児から高齢者まで誰もが必要とする普遍的な飲み物です。したがって「水が不衛生で飲めないので、代わりにワインを飲んだ」という説明を字義どおりに受け取ると、「子どもから老人まで、全員がワインで水分摂取しなければならなかった」状況を前提にしてしまいます。
しかしこれは生活感覚としても整合しにくいものです。
それでもこの話が流通するのは、
- 頭の中の主語が実際には“健康な成人”に置き換わったまま「人々一般」に言い換えられること
- 「特定条件で水が不快/危険」だった話が「水は飲めない」に飛躍すること
- 「水vsワイン」の二択に圧縮されて他の選択肢が消えること
- 「薄めたワイン/低アルコール飲料」の断片が“全員必須”の話として誤読されやすいこと
が重なっているためです。
特に雑学・入門コンテンツの書き手は短い“それっぽい話”を求めるため、目的が「正確さ」ではなく「面白さ/覚えやすさ/盛り上がり」になりやすく、反例(幼児・高齢者)を入れて整合性を検証する工程が最初から抜け落ちがちです。
結論として、不衛生な水にワインを混ぜても、アルコールで殺菌されて安全に飲めるようになる、とは考えにくいです。
アルコールの濃度が足りません
手指消毒などの「消毒・不活化」の文脈では、エタノールは一般に 60–95% 程度で有効性が論じられ、少なくとも ≥60% が目安とされます(CDCの手指消毒の解説など)。
一方、ワインは通常 10–15% 前後で、さらに水で割ればアルコール度数はすぐ下がります(例:12%を1:1で割ると約6%)。この濃度域では、消毒に必要とされる前提(≥60%程度)を満たしません。したがって、「不衛生な水にワインを混ぜればアルコールで殺菌され、飲めるようになる」という説明は成立しにくいです。CDC.GOV
要するに、「汚い水に混ぜたら、アルコールで殺菌されて飲めるようになる」という発想の前提(十分な濃度)が成立しません。
「低濃度でも効く」は状況依存で、飲料の安全化には使えません
低濃度エタノールが一部の条件で菌の増殖に影響することはあり得ますが、効果は微生物・環境・接触時間で大きく変わり、しかも「安全な飲用水にする」ほど確実なものではありません。低濃度エタノールの影響は条件依存で、飲料を「飲用可能にする」ほど一貫した効果を期待するのは難しいです。
この幅を見るだけでも、「ワイン+水」の数%〜十数%程度のアルコールに“水の安全化”を期待するのは無理があります。
ワインの「抗菌性」は研究されていますが、水を飲用可能にすることにはなりません
ワインはアルコール以外にも、低いpH(酸性)や有機酸、(とくに赤ワインの)フェノール類など、微生物に不利に働く要素を持ち、抗菌効果を示す研究はあります。
ただし、これは「ある条件で菌数が減る/増殖が抑えられる」といった話であって、不衛生な水を“飲用可能にする工程”として安定運用できるという意味ではありません(しかも水で薄めれば酸もアルコールも薄まり、効果はさらに読みにくくなります)。
では「水で薄めたワイン」は何だったのか
「水で薄める」行為が語られる場合でも、それを殺菌手段として説明する根拠は弱く、むしろ「強さの調整」「飲みやすさ」「量を増やす」「食事と合わせる作法」などの説明のほうが整合的です(少なくとも“殺菌できるから”と直結させるのは飛躍になります)。
古代ギリシャ:少なくとも古典期アテナイのシンポシオンでは、加水が作法として強く組織化される
古代ギリシャの宴飲(シンポシオン)では、ワインは水と混ぜて供するのが基本で、会場中央のクラテル(混和器)で混ぜ、濃さは主宰者(symposiarch)が決める、という説明が美術館の概説に明確です。
この文脈では「水で薄めたワイン」は妥協策ではなく、節度・統制のある飲酒作法として機能していました。
古代ローマ:ローマでも、冷水・温水で薄める飲み方が一般的
ローマ側でも「(ギリシャ人と同様に)ワインを水で薄めて飲む」ことが、オックスフォード系の概説で一般論として述べられています。しかも冷水だけでなく温水で薄めることも含めて整理されています。
※関連してよく出る posca は、狭義には「水で薄めたワイン」というより、酢(または酸っぱいワイン相当)+水の飲料として説明されます(兵士の配給などの文脈)。
現代でも地域限定で残る:ドイツ語圏の Weinschorle/オーストリアの G’spritzter
「現代ではほとんどない」と言い切れるほどではなく、ドイツ語圏では今も一般的に見られます。
- Schorle:ミネラルウォーターで混ぜたワイン(またはジュース)
- Weinschorle:ミネラルウォーターで混ぜたワイン
- オーストリアの G’spritzter(Spritzer):表示規定上「≥50% ワイン、≤50% ソーダ水またはミネラルウォーター」
結論から言うと、「無加水で飲む文化がローマ時代以降に初めて広まった」とは言いにくいです。むしろ、ワイン自体はギリシャ・ローマ以前から広域で造られ飲まれており、そのうえでギリシャ・ローマ文化圏が“水割り(加水)を作法として強く規範化した”、という並びで捉えるほうが筋が通ります。
ワインはローマ以前から存在し、飲まれていた
ブドウ酒(grape wine)の成立はギリシャ・ローマよりはるかに古く、たとえば南コーカサス(ジョージア)新石器時代の土器に残る成分分析から、紀元前6000年紀(おおむね 6000–5800 BCE)にさかのぼる「ブドウ酒・ブドウ栽培」の証拠が示されています。
つまり、ローマ以前にも「ワインを飲む」こと自体は確実にありました。
ギリシャ文化圏で「加水」が宴席作法として制度化される
古典期アテナイのシンポシオンでは、ワインは通常水で割り、クラテル(混和器)で混ぜ、進行役(symposiarchos)が比率や杯数を決める、という枠組みが明確に説明されています(例:水3に対してワイン1〜2など。比率は場面・資料で揺れます)。
ここで重要なのは、これは「仕方なく薄めた」ではなく、節度・統制のある飲酒を支える“作法の中核”として語られている点です。
「無加水」は“他者”や“過度”として語られやすい(ただし現実は多様)
古代の言説では、無加水飲用(unmixed wine)が「好ましくない飲み方」と結びつけられ、barbarian(非ギリシャ/非ローマ的な他者)や「酩酊」と関連づけて語られる傾向が指摘されています。
ただし、ここは注意が必要で、こうした記述はしばしば文化的境界を引くための語り(ステレオタイプ)でもあります。
現実の飲み方は地域・階層・場面で揺れ、ギリシャ・ローマ文化圏の外側を一様に「無加水」と断定することはできません(※ただ「無加水で飲む人々がいた」可能性自体は、こうした言説が成立する前提でもあります)。
中世:baptizare が「ワインに水を入れて薄める」の意味でも使われる
中世になると、baptizare(本来「洗礼を授ける」)が、宗教的意味に加えて、ワインへ水を注いで薄める行為を指す語としてもしばしば用いられた、と整理されています。とくに居酒屋・商いの場面では「水増し(薄め)」と利益の問題が結びつき、混和を禁じる規定が繰り返し現れる、という文脈で論じられます。
この点は、「ギリシャ・ローマで確立した“加水作法”」が、その後も形を変えながら社会生活の中で可視化され、語彙化(baptizare)するほど身近な行為になっていた、という理解につながります。
結論から言うと、水割り文化の中心(少なくともギリシャのシンポシオンやローマの宴席の説明)では、「水で割った状態のほうが、飲み心地として“ちょうどよい(well-balanced)”」という発想がはっきり見えます。少なくとも「水を入れる=台無し」という感覚とは逆向きです。
古代ギリシャ:水割りは“ちょうどよい濃さ”=快い飲み物に整える操作
メトロポリタン美術館の教育用リソースでは、シンポシオンで主宰者(symposiarch)が水とワインの比率を決め、比率は「3:1〜3:2」あたりで揺れる、と説明したうえで、「A well-balanced mixture of wine and water brought conviviality and relaxation」(よく釣り合った混合が、くつろいだ場をもたらす)と述べています。
ここでの “well-balanced” は、単なる儀礼ではなく、濃さ(=味の強度、飲みやすさ)を“良い塩梅”にするという感覚を含む言い方です。
同じ資料にはアルカイオス(前7世紀)の詩として「水2:ワイン1で混ぜよ」という具体的な呼びかけも引用されており、混ぜる比率が「味の好ましさ(濃さの良し悪し)」として語られ得たことが示唆されます。
なお、別の同館解説では「通常は水3〜4:ワイン1」とも説明され、比率は一つに固定されていません。
古代ローマ:水割りは「好みの濃さ」に調整する前提で語られる
ローマの宴席についてメトロポリタン美術館の解説 “The Roman Banquet” は、ワインを飲む前に水で混ぜ、温水や冷水(場合によっては雪や氷)も用いたこと、そして典型的には各客が自分の杯で、好みの味になるように混ぜたことを述べています。
この説明からは、水割りが単なる規範ではなく、味(濃さ・飲み心地)を好みに合わせて整える操作として理解されていたことが分かります。
まとめ
したがって、水割り文化の中核では、少なくとも理念としては、「水を入れると味が壊れる」ではなく、「水で濃さを整えることで、よりバランスのよい(=飲み心地のよい)味になる」という方向の理解が成立していた、と言えます。
はい、現代でも 「完成したワイン(グラスに注いだ後)に、ごく少量の水を足すと、場合によっては香りや飲み心地が良くなる」という肯定的な意見はあります。
ただし、これは主流ではなく少数派で、対象は主に「アルコールが強すぎて熱さが前に出る」「重くて香りや果実感が取りにくい」といったタイプに限って語られます。
「完成したワインへの加水」を肯定的に述べている例
- Dan Berger(米・ワイン評論家)
- 高アルコールで灼けるように感じたワインに対し、グラスに大さじ1杯ほどの水を加えたところ「問題が解決した」と書いています。香りを損ねるのではなく、アルコールが果実を覆っていたのがほどけて「少しフルーティに感じた」、熱さも和らいだ、という趣旨です。
- John Wilson(The Irish Times/ワイン筆者)
- 「数滴〜小さじ程度」の加水が、場合によってはワインを良くすると述べています。自身も「big red」に小さじ1〜2杯の水を足したら、香りが増し、ジャミーな重さがよりフレッシュな果実に感じられたと書きます。
- 一方で、入れすぎると「dry and hollow」に寄るので、量を抑え、良いボトルにはしない、と副作用も明記しています。
- Michel Chapoutier(ローヌの著名生産者)
- 気候変動と高アルコール化の議論(rehydration)の流れの中で、報道では「2003年の超凝縮したワインでは、軽さとフィネスを取り戻すためにグラスに小さじ1杯の水を足したことがよくあった」という具体例が紹介されています。
どんな理屈で「良くなる」とされるか(味わいに限って)
肯定的な説明は概ね共通で、アルコールの刺激(熱さ)が強すぎると香りや果実の輪郭が取りにくい → ごく少量の加水で刺激が下がり、香りや果実が感じやすくなる、という筋立てです。
なお、今回の主題である「完成したワインへの加水」は少数派ですが、別枠として マスト(発酵前の果汁)への加水は温暖化対応の文脈で議論が比較的多く話題に上がります。
関連ページ
- posted : 2025-12-28
- Author : katabami (Editor) / ChatGPT + Gemini (Writing Assistant)
- ワイン教育(WSETなど)における「Training(仕立て)+ Pruning(剪定)」の関係 « HOME » ラングドック・ルシヨンにおけるぶどう栽培の成立・拡大・単作化