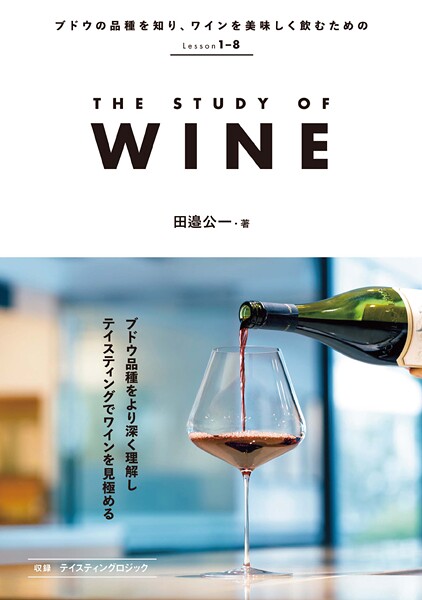オー゠メドックでのカベルネ・ソーヴィニヨンの立ち位置
「Carmenet(カルメネ)」という語の二層構造
Carmenet は、歴史的用法と学術的用法の二つの側面を持つ語です。
- 歴史的用法 ― メドックでの Cabernet Franc の古名
- ボルドー、とくにメドックでは、Cabernet Franc が古く “Carmenet” と呼ばれていたとされます。
- 文献上も 18–19世紀にかけて Vidure/Bidure/Carménet などの異表記が混在し、当時のカベルネ系品種の呼称がまだ整理されていなかったことがうかがえます。
- 学術的用法 ― Levadoux(1948)の eco-geogroup
- 1948年、フランスのアンペログラファー Louis Levadoux は、フランスに伝わる多数の在来品種を遺伝的・地理的まとまり(éco-géogroupes)として分類しました。
- その中でカルメネ群は、ボルドー周辺〜バスク地域にまたがる歴史的交雑圏を背景にもつグループとされ、現在のDNA研究とも整合する内容を含んでいます。
- Levadoux の Carmenet eco-geogroupとして挙げられる品種
- Cabernet Franc
- Cabernet Sauvignon
- Carmenère
- Gros Cabernet
- Merlot
- Merlot Blanc
- Hondarribi Beltza
カベルネ・ソーヴィニヨンがメドックで主力になったのはいつ頃か
18世紀後半には最上級シャトーのワインにおいて、カベルネ・ソーヴィニヨンが非常に大きな比重を占めていたことが示唆されます。
また、19世紀に入るとボルドーの赤のスタイルがマルベック中心からカベルネ・ソーヴィニヨン/メルロへ大きく移ったという記述があり、この時期に「主要品種としての地位」が広く確立していったと見るのが自然です。
その根拠になり得る観点
- 1) 18世紀のグラン・ヴァンのブレンド証言
- UC Davis のまとめによれば、1988年に行われたシャトー・マルゴーの歴史的ヴィンテージ試飲で、1771年・1791年などのブレンドがカベルネ・ソーヴィニヨン中心(例:75%)だったとされています。
- これは「当時の畑の植栽比率」を直接証明する資料ではないものの、少なくとも18世紀後半のトップ・メドックにおいて、カベルネが“完成形のワイン像”の核に置かれていたことを強く示唆します。
- 2) 19世紀の「スタイル転換」
- 同じく UC Davis の Malbec 章では、19世紀にボルドーの赤のスタイルがマルベックからカベルネ・ソーヴィニヨン/メルロへ大きく変化した理由としてマルベックの不作が続いたことなどが挙げられています。
- ここからの推論として、病害・不作リスクの管理と品質安定の観点が、カベルネ(+メルロ)への重心移動を後押ししたと読むことができます。
- 3) 「カベルネは遅熟で、メルロは早熟」という成熟カレンダーの組み合わせ
- この観点は土壌よりも気象リスクとワイン設計の話です。
- 遅熟のカベルネは年による振れ幅が出やすい一方、早熟のメルロは収穫の安全弁として機能します。
- メドックの上位シャトーが歴史的に「カベルネ主体+メルロ補助」を磨いてきた構図は、成熟時期の異なる品種の組み合わせでヴィンテージ変動を吸収するという実務的合理性でも説明できます。(この点は上記2)の「不作がスタイルを動かした」という記述と整合的です。)
結論から言うと、カベルネ・フランは右岸では重要な補完品種として存在感が大きい一方、メドックでは歴史的にも主役になりにくく、基本的に補助的な位置づけにとどまってきたと考えるのが自然です。
左岸(メドックを含む)ではカベルネ・ソーヴィニヨンが支配的で、メルロ、プティ・ヴェルド、マルベック、カベルネ・フランは一般に補完的役割に位置づけられる、という整理が広く示されています。
右岸でのカベルネ・フランの意味
右岸の赤はメルロ中心で、カベルネ・フランが
- 香りの複雑さ
- 酸の輪郭
- スタイルの引き締め
といった要素を補う設計が伝統的に有効だと理解されています。
このため、右岸におけるカベルネ・フランは「脇役」ではなく、メルロの相棒としての重要度が高い補完品種と言えます。
メドックで主役になりにくい理由
メドックはカベルネ・ソーヴィニヨンが骨格を作りやすい条件と結びつき、左岸のブレンド設計は“カベルネ・ソーヴィニヨンを中心に据える構造”が基本形と説明されます。
この枠組みの中でカベルネ・フランは、
- 香味や構造の微調整
- ヴィンテージ差の緩衝
といった役割に回りやすく、「主役ではないが意味のある補助品種」という位置づけが妥当です。
マルベックの比重が大きかった時代はどうか
マルベックは19世紀以前のボルドーで重要品種で、19世紀にマルベック中心のスタイルからカベルネ・ソーヴィニヨン/メルロへ大きく移行したという説明が、UC Davis の整理で示されています。
この史実から逆算すると、メドックでも当時はマルベックの比重が現在より大きかった局面があったと見るのが自然です。
ただし、その時代にカベルネ・フランがメドックの“第一主役”に立っていたことを示す強い根拠は、少なくとも一般向けの整理では見当たりません。
したがってここは仮説段階ですが、マルベックがより重要だった局面を含めても、メドックの中心は別品種(当時はマルベック、その後はカベルネ・ソーヴィニヨン/メルロ)に置かれ、カベルネ・フランは主に補完的役割にとどまったとまとめるのが、現時点では最も無理のない理解だと思います。
影響した可能性は高いです。
ただし、「干拓が直接カベルネ・ソーヴィニヨン植栽を決めた」という単線的因果ではなく、干拓が“カベルネ・ソーヴィニヨンが主役になり得る土地条件を広げた”と理解するのが最も無理のない整理です。
メドックは17世紀まで湿地が多く、オランダ系技術者による排水・干拓が進むことで栽培に適した土地が急速に拡大したと説明されています。
この事実から、過湿が軽減され、実質的に地下水位がコントロールされることで、ブドウ栽培の安定性が上がったと推定するのは機能的に自然です(この点は推論)。
また、メドックは河口寄りの砂利質地帯と結びつく産地であり、排水の良い砂利系の土壌がワインの個性形成に重要だとされてきました。
公式解説でも、カベルネ・ソーヴィニヨンは砂利質で成熟しやすく、条件が悪いと熟しにくいことが示唆されています。
したがって、干拓は
- 湿地の制約を減らし
- 砂利を含む栽培適地の利用を拡大し
- 結果として遅熟で骨格型のカベルネ・ソーヴィニヨンが成功しやすい舞台を整えた
という意味で、メドックにおけるカベルネ・ソーヴィニヨン拡大の重要な前提条件の一つだったと位置づけられます。
はい。バ・メドックでも、砂利が厚く堆積した区画ではカベルネ・ソーヴィニヨンが好んで植えられやすい、と考えてよいと思います。
AOC Médoc の公式解説でも、メドック北部の軽い砂利の沖積テラスはカベルネに適し、より深く粘土的な土壌はメルロに適するという整理が示されています。
また、メドック全体の歴史として、17世紀にオランダ系技術者が湿地の排水を進め、砂利の尾根を含む土地がブドウ栽培に利用可能になったという説明は広く共有されています。
このため、排水改善の恩恵が相対的に大きかった北部ほど、砂利の優良区画が本格的にワイン用ブドウへ転用されやすくなったという見立ては自然です(この部分は地史的機能に基づく推論)。
ただし重要なのは、バ・メドックという地域名だけで品種を決め打ちしないことです。北部は砂利だけでなく粘土比率の高い区画も多く、実際の品種構成は砂利の小丘(croupe/butte)など“砂利のまとまり”の有無で大きく変わります。
具体例(北部でも“砂利ならカベルネが成立する”ことの裏づけ)
シャトー・ポタンサック(Château Potensac)はバ゠メドックにあり、 Merlot 48% / Cabernet Sauvignon 33% / Cabernet Franc 18% / Petit Verdot 1% という植栽構成を公表しています。
北部でもカベルネ・ソーヴィニヨンが“補助の域を超える比率”を持ち得ることを示す好例です。
シャトー・ルデンヌ(Château Loudenne)では、ジロンド川の河口の汽水域(内海のように広がる水域)に近い、砂利の非常に豊かな2つの小丘にブドウ畑があり、砂利に粘土が混じり、その下に石灰岩台地があると説明されています。
こうした立地は、メドック北部でも左岸的にカベルネ・ソーヴィニヨンを活かしやすい区画が成立することを分かりやすく示します。
はい、影響しています。メドックの沿岸部と周辺では、風で内陸へ移動する砂を止めるため、18世紀末から試行的な砂丘固定が始まり、19世紀にかけて植生・植林が広域に進みました。これにより、砂が川や運河を塞いで湿地を悪化させる状況の改善が図られ、沿岸の景観と土地利用が大きく変わりました。
一方、1857年6月19日法は、主に内陸のランド地方の広い荒地を排水して森林化・農地化することを目的とした政策で、結果としてマリティム松(Pin Maritime)中心の大森林が拡大しました。
こうした森林帯は現在も、
- 大西洋からの強い風・嵐・塩分を含む空気の直接的な影響を弱める
- その結果、ジロンド河口側のブドウ畑が比較的安定した温和な海洋性気候の恩恵を受けやすくなる
といった形で、メドックの栽培環境を支える要因の一つになっています。
補足すると、防風林(砂丘の植生・植林)が本格的に整備される以前は、大西洋側の沿岸で移動砂丘や飛砂の影響が強く、強い海風が内陸の土地利用や作物にとって大きな負担になりやすい環境でした。
こうした沿岸環境の安定化が進んだ結果、同じメドック内でも南寄りのオー・メドックは、ジロンド河口の温度緩衝に加え、大西洋側の砂丘・マツ林帯による風の緩衝の恩恵が比較的安定して及びやすいと考えられます。
また、バ・メドックは防風林の整備が進んだ現在でも海洋の影響を相対的に受けやすく、風が強い年や涼しい年の影響が出やすいと説明されることがあります。
こうした条件差が、一般にオー・メドックのほうが成熟の安定性や評価で優位に語られやすい背景の一つになっています。
いいえ、「砂利質はメルロに向かない」とは言えません。
より正確には、砂利質はカベルネ・ソーヴィニヨンに強い優位性を与えやすい一方で、メルロも条件次第で十分に高品質を生みますという関係です。
メドックの説明でも、軽い砂利の沖積テラスはカベルネ向き、より深く粘土的な土壌はメルロ向きと整理されています。
これは品種の“絶対的な禁止・不適”ではなく、成熟の確度やスタイル形成の上での相対適性を示す表現です。
実際には、砂利が厚い区画でも、下層に粘土やシルトなどがあり適度な水分保持が確保される場合、メルロは左岸でも重要な構成要素として十分に機能します。
一方、非常に乾きやすく温まる砂利主体の区画では、メルロが熟しすぎやすいリスクが相対的に増えるため、栽培管理や収穫判断がより重要になる、という理解が現実的です。
まとめると、砂利は“メルロ不向き”ではなく、砂利の厚み・下層の性質・区画の微気候によってメルロの適性が大きく上下する土壌だと捉えるのが最も正確です。
この違いは、土壌や成熟条件だけではなく、オー・メドックの上位シャトー、とくにクリュ・クラッセが築いてきた「カベルネ主体のスタイル規範」が強く作用している点に大きく由来すると考えられます。
左岸は多くの参考書で「カベルネ・ソーヴィニヨンが主要品種とされていた」という図式で語られます。
その図式が現在まで持続する重要な理由のひとつが、オー・メドックのクリュ・クラッセが“骨格と熟成力を核とする伝統的スタイル”を自己規範として守り続けてきたことです。
クリュ・クラッセのスタイルが品種構成を支える
オー・メドックのクリュ・クラッセは歴史的に、カベルネ・ソーヴィニヨンを構造の中心に据え、メルロで質感や中盤を補うという設計で評価とブランドを築いてきました。
このため、「期待される味わいの型」が、カベルネ比率を一定以上に保つ方向へ働くという力学が生じやすいと整理できます。
この点は市場心理やブランド維持に関わるため、仮説段階ですが、オー・メドックでカベルネが重要品種として残り続ける理由を説明する際の有力な補助線になります。
中核区画の性格が“規範”を現実にする
オー・メドックの評価を形づくってきた中核的区画には、カベルネ・ソーヴィニヨンが品質と個性を発揮しやすい砂利の微高地が多く含まれます。
この地形・区画の強みが、クリュ・クラッセのスタイル規範を実務として成立させる基盤になっています。
グラーヴ/バ・メドックでは別の合理性が前に出やすい
一方で、グラーヴやバ・メドックは地域内の区画条件や生産スタイルの幅が大きく、クリュ・クラッセのような強いスタイル規範が産地全体に同じ密度で作用するわけではありません。
その結果、より早熟で適応幅の広いメルロを増やす判断が、経営やリスク管理、目指すスタイルの観点から合理的になりやすい局面があると整理できます。
この問題の一番大事なポイントは、AOC名としての「Médoc」と「Haut-Médoc」が並立した結果、通俗的・教育的な理解のレベルで「Médoc=(旧)Bas-Médoc」とみなされやすくなったという“認知のズレ”にあります。
制度の出発点:AOC Médoc は広域アペラシオンとして成立
AOC「Médoc」は1936年11月14日の政令で認定されたことが、仕様書で明記されています。さらに仕様書の地理的説明では、ボルドー北方の左岸に沿って長く伸びる広域アペラシオンとして描写され、約80km・50コミューン規模の範囲が示されています。
このため制度上は、「Médoc」というAOC名が“メドック地方の広域”を射程に入れているという理解がまず前提になります。
しかし“見え方”を変えたのが Haut-Médoc という枠
教育資料では地理の説明として、サンテステフ以北ではアペラシオンが“単にAOC Médocになる”、そしてそのエリアは“かつてBas-Médocと呼ばれていた”と整理されています。
つまり教育・通説レベルでは、Haut-Médoc が南側の核を担う→ 北側が“単にMédoc”として残る→ その北側が旧Bas-Médocと重なるという図が、非常に分かりやすい形で提示されているわけです。
この構造が、「Médoc は Bas-Médoc から“Bas”を取ったもの」という理解を自然に生みやすくします。
実務・市場がこの“短絡”をさらに強めた可能性
同じ教育資料は、AOC Médocは“技術的にはメドック全体をカバーする”が、実際のワインは“Haut-Médocの北側(旧Bas-Médoc)に多い”という趣旨を述べ、1970年代半ば以降の栽培拡大にも触れています。
この種の説明は、“制度上の広域性”よりも市場で目にするラベルの頻度が人々の理解を決めてしまう現象をよく表しています。
結果として起きたこと
以上をまとめると、誤解の生成過程は次の通りです。
- AOC Médoc は広域アペラシオンとして成立。
- 同時に Haut-Médoc が南側の中核的表示を担う枠として機能。
- 南側は Haut-Médoc や村名AOCが前面に出やすく、“単独で Médoc と表示されるワイン”が北側に集中して見える。
- 北側は歴史的に Bas-Médoc と重なるため、“Médoc=Bas-Médoc(からBasを取ったもの)”という理解が定着しやすくなる。
これは日本だけの傾向か
少なくともこの説明枠は、英語圏の教育的整理でも同型の理解が提示されているため、日本特有というより「制度名の並立が生む国際的に自然な整理(と誤解)」と捉えるほうが無理が少ないと思います。
関連ページ
- posted : 2025-12-09, update : 2025-12-09
- Author : katabami (Editor) / ChatGPT (Writing Assistant)
- ワイン産地としての「シャブリ」の基礎知識 « HOME » リースリングとペトロール香