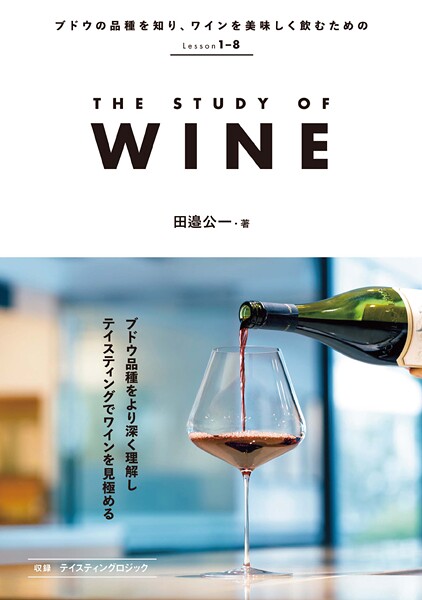ワイン産地とぶどう品種の関係性はどのように生まれたのか
産地と特定品種の結びつきが「いつから始まったか」は、(1)認知・言説、(2)実務・市場、(3)法制度、という三つのレベルに分けて考えると整理しやすいと思います。
- 認知・言説のレベルでは、中世末〜16世紀に、ブルゴーニュなど一部地域で品種名が史料に現れ、特定品種への評価が語られ始めた段階を出発点とみなせます。
- 実務・市場のレベルでは、19世紀にアンペログラフィー(品種誌)とフィロキセラ後の再植栽を通じて、「ブルゴーニュ赤=ピノ」「バローロ=ネッビオーロ」など、主要産地の代表品種が事実上かなり固まります。
- 法制度のレベルでは、フランスの AOC(1930 年代〜)、イタリアの DOC(1963 年〜)が、それまでの慣行を法的に書き起こし、「産地名+品種構成」を制度として固定しました。
年代の切り方は、現時点の文献からの推定に基づくもので、厳密な線引きというより仮説段階と考えてください。
中世末〜16 世紀:品種名が史料に現れ始める段階
古代ローマの文献には Aminea などブドウの名前が出てきますが、これは今日の「単一品種」を厳密に指すというより、ゆるやかな系統名やグループ名である場合が多いとされています。ここで扱うのは、現在のブドウ品種の概念にかなり近いかたちで名前が記録され、それが特定の産地や品質評価と結びつき始める時期です。
中世ヨーロッパでは、ワインは「ブルゴーニュ」「ボルドー」「ディジョンのワイン」といった地名で呼ばれるのが普通で、ブドウ品種名はほとんど前景に出てきませんでした。ただし、ブルゴーニュのような一部の銘醸地では、13〜14 世紀あたりから品種名が公文書や記録に現れ、品種ごとの評価が記述されるようになります。研究によれば、noirien(ノワリアン)、tressot、gamay、pinot などの名称が中世末の史料に登場し、産地名とあわせて語られていることが示されています。
よく知られている 1395年のフィリップ豪胆公の勅令は、収量は多いが低品質とみなされたガメイを上質な畑から排除するよう命じたもので、上級区画から高収量品種を追い出そうとする政策的意図が読み取れます。ただし、勅令本文はピノ・ノワールという名前を直接挙げておらず、「ガメイ排除=ピノの指定」とまでは言えません。ガメイに対置される「高品質の黒ブドウ」がのちにピノ系統と同一視されていく、というのが現在の慎重な解釈です。
この時期は、まだ「産地=ひとつの品種」という構図ではなく、「一部の上質なクリュには、ある種の『良いブドウ』がふさわしい」という、ごく局所的でエリート層中心の発想が芽生えた段階と捉えるのが妥当だと思います。
16〜18世紀:土地にふさわしい品種をめぐる議論の時代
16〜18世紀になると、農業書や自然誌が各地方の栽培状況をまとめるようになり、「この地方ではこういうブドウが高く評価されている」といった記述が増えていきます。品種名と地名が、観察や推奨のレベルで結びつけられる場面が目立ち始めるのはこの頃です。
それでも畑レベルでは複数品種の混植が続きますし、ワインが市場で区別されるときも、「ボルドー」「ブルゴーニュ」「キアンティ」といった地名が主であり、品種はその背後にある要素の一つにとどまっています。言い換えれば、この時期は「産地ごとに好ましいブドウのイメージが、学者や栽培家の言説として少しずつ整っていく」段階であって、まだ現在のような強いペアリングには達していません。
19世紀:実務レベルで「産地=代表品種」が強まる段階
今日私たちがイメージする「ブルゴーニュ赤=ピノ・ノワール」「バローロ=ネッビオーロ」「トスカーナの高級赤=サンジョヴェーゼ」といった組み合わせが、実務と市場のレベルでかなりはっきりしてくるのは、主に19世紀です。ここで挙げているのは、それぞれの産地における「主力・代表品種」という意味であって、法令上ほかの品種が完全に排除されている、という意味ではありません。
まず、1800年前後からアンペログラフィー(ブドウ品種誌)が発展し、各品種について「どの地方で栽培され、どう評価されているか」が系統的に記述されるようになります。こうした文献は、「各地方にはその地方らしい代表品種がある」という見方を、行政・学者・栽培家のあいだで共有させる役割を果たしました。
さらに19世紀後半のフィロキセラ禍により、ヨーロッパの多くのブドウ畑が壊滅し、接ぎ木による全面的な再植栽が必要になりました。その過程で、多くの地域が「この土地の主力品種はこの少数に絞ろう」と選択し、従来の混植・雑多な品種構成から、少数の主力品種への収斂が進みます。ブルゴーニュでピノ・ノワールがコート・ドールの高級赤にほぼ一本化していく過程や、ピエモンテでネッビオーロが高級赤ワインの中心的品種として位置づけられていく過程などは、その典型例です。
この結果、20世紀初頭には、主要産地の内部では「この地域のワインといえば、だいたいこの品種構成」という事実上の標準がかなり出来上がっていたと考えられます。ただし、地域・村・畑ごとの実情はかなりばらつきがあり、その全体像を一枚岩として描くことはできないので、この点は仮説段階とみなすのが安全です。
20世紀前半〜中頃:AOC・DOC による制度としての固定化
20世紀前半から中頃にかけて、フランスとイタリアで確立された AOC・DOC の制度は、それ以前に実務と慣行の中で形を成していた「産地=代表品種の組み合わせ」を、国家レベルの法制度として固定する役割を果たしました。
フランスでは、1905年8月1日法が食品・飲料全般について原産地や本質的性質を偽る行為を禁止し、不正・偽装防止の一般枠組みを整えました。この段階では、まだ「原産地呼称」が中心概念とは言えません。続く1919年5月6日法が、アペラシオン・ドリジーヌ(原産地名称)を法的に保護する最初の包括法として位置づけられ、典型的産品の地理的名称を守る枠組みを整えます。
転機となるのは1935年のデクレ=ロワ(7月30日)で、ここでアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ(AOC)とそれを審査する機関(のちの INAO)が創設されます。1936年以降、個々の AOC について生産規定が作成され、産地の範囲、栽培方法、収量上限に加えて、認められるブドウ品種とその割合が明文化されました。これにより、それまで地域の慣行や市場の常識として存在していた「このアペラシオンではだいたいこの品種(群)」という関係が、初めて全国的な法制度のなかで一貫して定義されるようになります。
イタリアでは、1930年代に「vini tipici(典型的ワイン)」と対応するゾーンを保護する法制が試みられましたが、施行上の問題もあり、全国的な体系としては十分機能しなかったと評価されることもあります。現在の DOC/DOCG 体系の出発点とされるのは 1963 年の D.P.R. 930/1963 で、この政令が “denominazione di origine controllata” および “denominazione di origine controllata e garantita” を定義しました。以後、各ワインについて原産地名・栽培区域・使用ブドウ品種とその割合などを disciplinare di produzione で定めることが義務づけられ、1960年代半ば以降の DOC 認定・DOCG 昇格のプロセスのなかで、具体的な産地ごとの規定が整っていきます。
このように、20世紀前半〜中頃の AOC・DOC 制度は、19世紀までに事実上成立していた「産地=主力品種」の組み合わせを、初めて全国一律の法制度として固定した段階、と整理できます。もちろん、多くの AOC/DOC は複数品種のブレンドを認めており、「1つの産地 = 1つの品種」に完全に還元できるわけではありませんが、代表的品種と産地名が制度的にも強く結びつけられたことは確かです。
まとめ
まとめとして押さえておきたいのは、産地と品種の結びつきが、長い時間をかけて段階的に形づくられてきたにもかかわらず、現代のテロワール論やマーケティングではしばしば、「この土地は太古からこの品種の唯一無二の故郷であり、その結びつきは昔から不変である」といった、きわめて強い物語として語られがちだという点です。
歴史学・社会学の文献(たとえば Hobsbawm & Ranger の “The Invention of Tradition” など)は、こうした物語の多くが、実際には19〜20世紀の制度化や市場競争のなかで再構成された「創られた伝統」であることを指摘しています。
歴史的には、ピノ系統とガメイの栽培比率や評価は時代ごとに揺れ動いてきたにもかかわらず、20世紀以降の言説では、「ブルゴーニュは昔からピノ・ノワールの産地であり、量を求めてガメイを植える者が後を絶たなかっただけだ」というかたちで、あたかもピノ・ノワールとの関係がほぼ一貫していたかのように語り直される傾向が見られます。
つまり、「この産地=この品種」という結びつきは、太古から自然に与えられたものというよりも、何世紀にもわたる栽培の変化・市場の評価・制度化の過程のなかで徐々に形成され、近代以降の物語のなかで「太古からの故郷」として再定義されたものだ、と理解しておく方がよいと思います。こう捉えておけば、のちにこの種の物語を批判的に検討するときにも、足場として使いやすくなります。
現在のゲノム研究をまとめると、ブドウ栽培の起点はおおむね二つの地域に置かれています。ひとつは西アジア(南東アナトリア〜レヴァント)で、もうひとつは南コーカサスです。Science に掲載された Dong らの大規模研究は、この二つの地域で約1.1万年前にほぼ同時に栽培化が起こった「二元栽培化」モデルを示しています。
一方で、Magris らや Xiao ら、Freitas らの研究は、「栽培化そのものは西アジアで1回起こり、その後ヨーロッパ各地の野生ヴィニフェラとの交雑が繰り返されて現在の西欧ワイン用品種ができた」という単一起源+広範な入戻し交雑モデルを支持しています。
細部のシナリオには違いがありますが、どちらの系統の研究でも、「東方で栽培化された系統がヨーロッパに入り込み、各地の野生ヴィニフェラと長い時間をかけて混ざり合った」という大枠ではほぼ一致しています。
イタリアの考古植物学者 Ucchesu らの研究でも青銅器時代から中世にかけて、野生型と栽培型の中間的な形質をもつ種子が多数見つかっており、「栽培 × 野生」がゆっくり混ざり合っていった像が裏づけられつつあります。
こうした背景の上で、「各ワイン産地で、その土地のブドウ品種がどう選ばれたか」を見るとき、まず押さえておきたいのは、昔はそもそも選べる品種の幅がとても狭かったという点です。各地域に初期に持ち込まれたのは、ごく限られた数の栽培クローンと、その周辺の野生ヴィニフェラと交雑して生じた少数のバリエーションに過ぎませんでした。
ローマ帝国期や中世の修道院ネットワークでも、「あの修道院で良いワインができる挿し木」「あの谷で霜に強いと評判の系統」といった、ごく少数の材料を互いに融通しながら増やしていったと考えられます。この「候補の少なさ」という視点は、現時点では考古植物学・遺伝学からの推測を含む仮説段階ですが、複数の研究が同じ方向を示しています。
次に重要なのが、ブドウという植物自体が思っている以上に柔軟で、多少条件が悪くても何とか生き延びて実を付けるという点です。ヴィティス・ヴィニフェラは温暖で比較的乾燥した地域を好むとはいえ、その周辺の環境でも栽培がまったく不可能というわけではありません。第四紀氷期後の分布をみると、野生ブドウはイベリア・イタリア・コーカサスなど南部のレフュジアで生き延び、その後、河川沿いや氾濫原、谷筋などさまざまな環境に再拡散したことが示されています。
これは、必ずしも「理想的な条件」だけにとどまらず、やや厳しい場所にも粘り強く張り付いてきた植物であることを意味します。
この二つの前提(候補の少なさとブドウの柔軟さ)を踏まえると、「その土地の品種」が選ばれるうえで長期的に効いてきたのは、だいたい次のような要因だったと整理できます。
第一に、その土地の気候・土壌で「枯れずに、ある程度安定して熟す」ことです。氷期のレフュジアからの再拡散パターンを見ると、冷涼な北限に近い地域では早熟で寒さに比較的強い系統が残り、内陸の乾いた地域では干ばつにやや強い系統が残るなど、環境に応じた地域差が見られます。そうした環境条件の中で、「この谷ではこの系統なら何とかなる」と判断されたものが世代を超えて残されました。
第二に、その土地の社会・経済にとって「使い道がはっきりある」ことです。ローマ帝国期には軍団補給や課税に耐えるだけの収量と酒精度が求められ、中世〜近世には聖餐用・貢納用・輸出用など用途ごとのワイン像がありました。そうした需要に応えやすい系統(酸が高く輸送に強い、濃色・高アルコール、甘口・長期熟成向きなど)が、修道院・領主・商人による選抜のなかで優先的に広がり、各地の「主力品種」として定着していきます。
第三に、遺伝的な偶然も大きな役割を果たしました。全ゲノム解析では、現代のヨーロッパのワイン用品種には、西アジア起源の栽培系統だけでなく、ヨーロッパ野生群からの遺伝子がかなりの割合で混ざっていることが示されています。これは、一度きりの単純な「栽培 × 野生」の交配ではなく、東から来た栽培系統が各地の野生集団と何度も交雑し、その都度「その土地で役に立つ組み合わせ」が人間の手で選び残されていった結果だと解釈できます。
こうして見ると、各ワイン産地で「その土地のブドウ品種」が選ばれた背景には、
- もともと選べる候補が非常に少なかったこと
- それでもブドウが意外にしぶとく、理想的とは言えない環境でも何とか育ってくれたこと
- その上に、気候・土壌・用途・遺伝的な偶然が長い時間をかけて折り重なったこと
という三つの条件が重なっていた、とまとめることができると思います。
フィロキセラ禍以降、「さまざまな制約の中での選択」が結果として産地の個性を形作った、という理解はかなり妥当だと思います。
19世紀のヨーロッパのブドウ畑は、うどんこ病(19世紀半ば)、フィロキセラ(1860年代以降)、ベト病(1878年以降)といったアメリカ由来の病害・害虫に次々と襲われました。フィロキセラへの決定的な対応策はアメリカ系台木にヴィニフェラを接ぎ木することであり、この時期を境に、ブドウ栽培は自根主体から接ぎ木前提へと構造的に転換していきました。
この再建の過程で、フランシュ=コンテなどに代表される「ブドウ苗木業」が1890年代以降に本格的な産業として立ち上がり、接ぎ木苗をフランス各地に供給するようになります。たとえばギヨーム家の苗木業は、フィロキセラ後のブドウ畑再建を背景に1895年に創業し、全フランスの産地に接ぎ木苗を出荷していたことが、自社史・地方史の両方から確認できます。
ただし、この段階でも「世界中の品種・クローンから自由に選べる」状況ではありませんでした。現実に各産地が使えた候補は、だいたい次のようなものに限られていました。
- もともとその産地や近隣で栽培されていたヴィニフェラ品種
- 当時利用可能だったアメリカ台木の中で、その土地の土壌・気候に何とか適応しそうなもの
- 苗木業者・研究機関が増やしやすく、市場や行政からも評価されやすい品種・組み合わせ
プレ・フィロキセラ期に存在していた在来品種のうち、病害に極端に弱い・手間のわりに収量や評価が低いと見なされたものは、接ぎ木と再植栽のコストに見合わないとして外されがちになります。
一方で、病害とある程度付き合え、台木との相性も許容範囲で、その土地の条件で安定して熟し、市場で評価されるワインを生み出せる品種が、接ぎ木苗と原産地呼称制度(のちの AOC/DOC など)を通じて広がっていきました。
19世紀に相次いだフィロキセラをはじめとする病害・害虫の被害が、現在のヨーロッパのブドウ遺伝資源や栽培構造を大きく形作ったことは、害虫・病害側の研究からも裏付けられています。
この意味で、現在の「この産地といえばこの品種」というイメージは、
- すでにその地域や周辺に存在していた品種の中から
- 病害・技術・苗木供給・市場・制度といった制約を考慮して
- 「ここならこれでやっていける」という現実的な組み合わせを選び、それが後に制度と物語によって固定された結果
と理解する方が実態に近いと思います。
したがって、「さまざまな制約の中での妥協が、かえって産地の個性を形作ったと言えるのか」という問いに対しては、「妥協」を「制約条件付きで選び取らざるを得なかった最善策」といった意味に広く取るなら、そう言ってよいと思います。
白紙状態から理想の品種を設計したというよりも、限られた既存品種と当時の技術・経済条件の中で選ばれた組み合わせが、その後「この土地=この品種」という個性として語られるようになった、という整理がいちばんしっくりくるのではないでしょうか。
「ドイツでは、その土地を代表するブドウ品種」という結びつきが相対的に弱く見えるのは、結びつきそのものが欠けているというより、結びつきが表れやすい“単位”と、その背景条件がフランスやイタリアと少し違うためだと考えるのが自然です。
第一に、ドイツにも強いペアリングはありますが、それが「村ごとに固定」より「産地全体(または大きめの地理単位)での支配的品種」として現れやすい点です。たとえばモーゼルはリースリングが6割強を占め、ラインガウもリースリングが圧倒的です。 つまり「この村=この品種」が弱い一方で、「この産地=この品種」が強い例はきちんと存在します。
第二に、気候条件です。ドイツは冷涼側に寄った産地で、年ごとの天候が収量・品質に与える影響が南の地域より大きい、とドイツワイン側の解説でも明示されています。 この条件下では、栽培の安全性(きちんと熟すこと、病害や腐敗リスク、収穫時期の読みやすさ等)を優先して、複数の品種を併用したり、結果として「多くの地域で共通に使われる品種セット」が形成されやすくなります。すると、村単位での“唯一の看板品種”は相対的に立ちにくくなります。
第三に、ドイツのワインは歴史的に、村単位よりも「川筋や地域帯」といった広域のまとまりで取引・評価されやすかった点です。英語圏でラインの白が Hock(Hochheim 由来)として総称されてきたことは、その一例としてよく挙げられます。 こうした広域単位での理解が強いと、個別の村が「この村=この品種」という形で知られるよりも、「この地域帯のワイン」というイメージが先に立ちやすくなります。
まとめると、ドイツで弱く見えるのは「結びつきがない」からではなく、①強い結びつきが“村”より“産地全体”で立つことが多い、②冷涼条件ゆえに共通品種・複数品種運用になりやすい、③広域の産地名で理解される歴史的慣性がある、という重なりによるもの——この整理がいちばん誤解が少ないと思います。
シャンパーニュでも冷涼条件のもとで「その土地で安定して熟す品種」へ収束していく力学は働きました。ただし、その収束の進み方と最終的な形は、ドイツと同じプロセスでは説明しきれません。
似ているのは、冷涼条件のもとで「毎年きちんと原料が取れること」が強い選別圧になり、フィロキセラ禍後の再植栽を通じて“勝ち残る品種”が整理されていった点です。一方で決定的に違うのは、シャンパーニュでは(遅くとも)19世紀までにスパークリングが地域の中核スタイルとして確立していく過程で、酸・成熟・圧搾適性・ブレンド設計といった要件に合う少数品種へ、産地全体が強く収斂しやすかったことです。公式の説明でも、19世紀後半の品質向上の動きのなかで主要品種が選ばれていった、という筋立てで語られています。
この「収斂の強さ」を理解する鍵として、ピノ系(Pinot Noir/Meunier など)だけで閉じた世界ではなく、かつては Gouais Blanc(Marmot などの呼称を含む)がシャンパーニュでも相当に栽培されていたのに、20世紀初頭にはごく限られた村に残る程度まで急速に後退した、という事実があります。
これは、産地が長期的に“淘汰と収斂”を強く受けたことを示す分かりやすい材料です。さらに Gouais Blanc は Pinot との交雑によって Chardonnay の親になったことがDNA研究で裏づけられており、結果としてシャンパーニュの基幹品種群の系譜そのものに深く関わっています。
この文脈で「スパークリング化が新しい品種を拒んだ」と言い切るのは因果が強すぎますが、少なくとも、スパークリングの要請と市場の期待が強い産地では、基幹品種が十分に機能している限り、育種品種や新規導入品種を“主力”として取り込んで更新する必要が相対的に小さくなり、既存の基幹品種へ投資が集中しやすい、とは整理できます。結果として、現在は3品種が植栽の大半を占める、という姿になります。
ドイツはシャンパーニュと違い、冷涼条件に対応できて品質と収量を両立しやすい品種であれば、比較的取り入れやすい側面がありました。この「取り入れやすさ」は、ドイツで「その土地を代表するブドウ品種」という結びつきが(とくに村単位では)弱く見えやすい要因の一つになり得ます。
ただし、それを単独の“主因”として据えるよりも、もともとの栽培文化とセットで考える方が自然です。ドイツ語圏では長い間、混植(複数品種を同じ畑に植える)や複数品種の併存が広く見られ、悪年でも「どれかは実る」ことを優先する合理性がありました。少なくともフランケンでは「1900年頃まで混植が普通で、その後に品種純粋(単一品種)へ寄った」という説明が見られます。 ここでは村ごとに単一品種へ固定する必然性が弱く、状況に応じて品種を入れ替える素地が最初から大きいと言えます。
その上で、冷涼地で経営を成立させるには、毎年の成熟の確実性、病害や腐敗リスクへの耐性、収量の安定が重くなります。結果として、品質の上限だけでなく「安定して得られる品質」を重視して品種を選ぶ傾向が強まり、(19世紀後半以降の)育種・選抜の進展も背景に、導入や入れ替えが起こりやすくなります。品種構成が動くこと自体が、ある意味で冷涼地の合理的な適応でもあります。
さらに重要なのは、単一品種ワイン(ヴァラエタル)として成立しやすいことです。ヴァラエタルであれば、地域性を「この村の固有品種」によって担保しなくても、品種名そのものがスタイルの説明になり、新しい品種が増えても“衝突”が起きにくい。これが、ドイツで「場所×品種」を排他的に固定する圧力を弱めます。結果として、リースリングやピノ・ノワールのような柱がある地域が存在しても、同時に別の品種が入り込む余地が残りやすい、という構図になります。
したがって、質問への答えはこう整理できます。ドイツでは「気候に適した品種を取り入れて品種構成が変化しやすい」ことが、結びつきを弱く見せる有力な要因であるのは確かです。ただし根っこには、混植・併存を許容する栽培史があり、その上で冷涼地としての安定性要求と、ヴァラエタルで説明できる市場慣行が重なって、導入・入れ替えの動きが強化された――この重なりが、ドイツの特徴を最もよく説明すると思います。
結論として、「産地名+品種構成」の固定化は、衰退を“決める”というより、環境変化に対する適応のコスト構造を変えると捉える方が正確です。GI名は、その時点で有効な仕様書(product specification)に基づいて使用が認められるため、品種構成を変えるには必ず仕様書の改定が前提になります。
仮に気候変動などで別品種の方が合理的になった場合でも、その導入には、当該品種が産地の典型性や品質と整合することを説明し、産地内外の合意を経て仕様書を改定する必要があります。したがって問題になるのは、「品種転換そのもの」ではなく、改定に要する説明・合意形成の負担と、その変更を市場が受け入れるかどうかです。
ただし、それでも「多くが衰退する」とは限りません。理由は3つあります。第一に、同一品種のまま適応する余地(台木・クローン選択、樹冠管理、収量設計、収穫タイミング、醸造での抽出設計など)が大きく、産地はまずここで“スタイルを動かしながら”生き残れます。
第二に、規格は硬直的に見えても、実務上は改訂が起こり得て、鍵になるのは「変更する/しない」をめぐる政治・合意形成と、変更を正当化する説明の組み立てです(そして、その説明が市場の期待と衝突しないかどうかです)。
第三に、経済面では、高いブランド価値を持つ産地ほど“品種を変えない適応”に投資でき、むしろ収量低下やヴィンテージ差の拡大を価格で吸収する方向に動きやすい一方、中価格帯以下では格下カテゴリ(より広域のGIや地理表示なし等)との二重構造が進みやすい、という形で「衰退」ではなく「階層化」として現れがちです。
したがって、単一品種(または少数主要品種)に強く依存する産地の将来は、
- その品種でどこまで品質様式を保てるか
- 規格改訂の政治的ハードルと産地内の合意形成
- 改訂で品種を動かす場合の市場の受容(あるいは代替カテゴリへ移った場合の価格形成)
の3点で決まります。
完全に「衰退」と言い切るより、“同じ名前のまま残る部分”と、“同じ名前の中身が少し変わる部分”、そして“別の名前で残る部分”が分かれていく、という見通しのほうが一般形としては扱いやすいと思います。
関連ページ
- ブルネッロとサンジョヴェーゼのクローン
- コート・ドールはピノ・ノワールを捨てることができるのか?
- ランブルスコとは
- ワイン産地としての「シャブリ」の基礎知識
- オー゠メドックでのカベルネ・ソーヴィニヨンの立ち位置
- posted : 2025-12-15, update : 2025-12-15
- Author : katabami (Editor) / ChatGPT (Writing Assistant)
- 世界で栽培されているワイン用ぶどう品種はどれくらいあるのか « HOME » ワインを言葉で表現することは必要なのか?