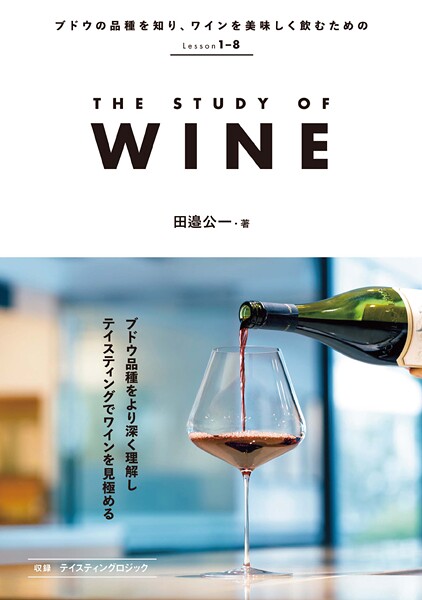ワインを言葉で表現することは必要なのか?
「香り・味を“細かい語彙で列挙する”書き方が、評論・教育・販売の場で目立つようになるのは、20世紀後半(とくに1970〜80年代)にかけて、と整理するのが安全です。象徴的な出来事として、Ann C. Noble らは、ワインの評価から主観的・情緒的な形容詞を排除し、誰でも物理的参照物(本物の果実など)で確認できる客観的語彙に統一することを目的に「Wine Aroma Wheel」を公表しました。
1970〜80年代は、業界・教育・評論で「共通の語彙を整える」動きが目立ち、香味を「構造(甘味・酸・タンニンなど)」と「具体的な香り・風味の言葉」を組み合わせて書く枠組みが整っていった時期、と言えます。いっぽう比喩が増えるほど「情報より演出が勝つ」危険もあるため、語彙の使い方(どこまで具体語が必要か)をめぐる議論はその後も続きます。
ただし、「花/果実」を使う比喩そのものは近代の発明ではありません。たとえば18世紀フランスの議論を引く形で、「raspberry bouquet(ラズベリーのブーケ)」のような表現が示されています。
18世紀の文脈では、むしろ「不健全なワインの匂い・味」の記述が大きな位置を占め、健全なワインについては甘辛・酸味など比較的粗い語彙に留まることも多かった、と指摘されています。したがって、現代のように“特定の果実名・花名を大量に並べる”書きぶりが、昔から常に主流だったとは言いにくいです。
同じテーブルで同じワインを飲んでいるなら、多くの場合「美味しい」「素晴らしい」だけで十分です。気分の共有という点では、それだけで会話は成立します。
ただし、同席していても、言葉にする意味が出る場面があります。違いは、その場に「追加の目的」があるかどうかです。
- 言葉がほとんど要らない場面
- 一緒に楽しむことが目的で、細部の確認や比較をしないとき。
- 言葉が役に立つ場面(追加の目的があるとき)
- 好みのすり合わせ:同じ「美味しい」でも、好きな理由が人によって違うため。
- 次の一本を選びやすくする:何が良かった(または苦手だった)かが残るため。
- 学習・検討:酸・甘味・渋味・アルコール感・ボディなどの“構造”を言うだけでも練習になるため。
- 記録:後日思い出す手がかりが増えるため。
このときも、花や果物の比喩まで使わなくても、「一言+理由」で十分に伝わります。
要するに、同席の「楽しむ場」では表現は必須ではありません。言葉が必要になりやすいのは、「楽しむ」以外の目的(共有・選択・学習・記録など)がその場に重なっているときです。
特定の「花名/果実名」が出なくても、まず問題ありません
香りの表現は「当てるゲーム」の必須項目ではありません。体系的テイスティングでも、香りは例示であり、全部を言う必要はなく、表現も「一般的」から「明確」まで段階として扱います。
したがって、出ないときは“出ない”が正解になり得ます。
「結び付けられない」ときの実務:比喩より先に“カテゴリ/構造”へ
特定名を無理に作る代わりに、次のどれかで十分伝わります。
- 香りの強さ・状態(弱い/強い、クリーンか等)
- カテゴリ止まり(例:フローラル系/柑橘系/核果系/ベリー系 など)
- 味わいの構造(酸・甘味・渋味・アルコール感・ボディ・余韻)
同席者が「花・果物」と言うのに自分には無いとき
まず「どちらかが間違い」と決める必要はありません。主な理由は次の3つです。
- 感度・閾値の個人差(嗅覚の強さは人によって大きく違います)
- 言葉による“誘導(期待・プライミング)”:先に提示された言語情報が、知覚や評価を動かし得ます。
- タイミング差(注いだ直後/少し空気に触れた後で立ち上がりが変わる等)
その場での対処としては、相手の言葉に無理に合わせようとせず、自分が確実に取れている要素(強さ、質感、構造など)を述べるだけで十分です。
どうしても確認したい場合でも、花名や果実名を「合わせる」ことを目的にせず、相手がどんな方向性(例:フローラル寄り/果実寄り/ハーブ寄りなど)として捉えているのかを、軽く確かめる程度に留めるほうが自然です。
要するに、比喩は“便利な翻訳”ですが、出ないときはカテゴリと構造に戻るのが最も安全で、同席の会話にも強い方法です。
はい、教育機関(スクール/資格講座)では結論が変わります。同席で同じワインを飲んでいても、「美味しい」「素晴らしい」だけで終わらせず、一定の枠組みで言語化すること自体が訓練の一部になります。
その中心になるのが SAT(Systematic Approach to Tasting:WSETの体系的テイスティング手順)です。WSETの教育・試験の文脈では、外観→香り→味わい→結論の順に観察し、甘味・酸・タンニン・アルコール・ボディ・風味の強さ・余韻などを、段階尺度(low/medium/high など)で選択して記述するという共通フォーマットとして機能します。
さらにディプロマでは、このSATに沿ってブラインドで記述・評価し、結論(品質、飲み頃、熟成可能性、文脈/同定に関わる推論など)まで書くことが試験で求められます。
教育の場で言語化が求められる理由は、要するに次の3点です。
- フィードバック
- 観察結果を共通の目盛り(SAT)で数値化・言語化することで、主観的な感覚のズレを「特定可能な誤差」として修正(キャリブレーション)できるようになります。
- 推論の可視化
- 感覚的な「結論」に逃げず、「どの構造要素(酸、タンニン等)が、品質や熟成可能性という結論を導いたのか」という論理的な因果関係を証明するために、言語化が必要となります。
- プロの評価基準
- 単なる試験対策ではなく、「なぜそのワインがその価格・評価に値するのか」を、他者が検証可能な形で提示する「専門家としての説明責任」を果たすための訓練です。
また、ここが重要ですが、教育の場でも「花や果物の比喩」を無理に捻り出す必要はありません。とはいえ上位レベルほど、“クラスタ(例:stone fruit)だけ”では点が伸びにくいという要請は強くなります。
WSETディプロマのガイドでは、まずクラスタ(例:stone fruit)で方向性を掴み、次に具体語(例:peach, apricot, nectarine)へ落とす手順が示されています。また採点は具体語に与えられ、上位レベルほど、クラスタ(例:stone fruit)だけよりも、より具体的な語(peach, apricot など)まで落とすほうが評価されやすい、という要請は強くなります。
要するに、同席の「楽しむ場」では沈黙(共有が成立している証になり得ます)や「美味しい」で成立しやすい一方、教育機関ではSATという共通フォーマットに沿って“書ける形”にすることが目的に含まれるため、同席でも言語化が必要になる、という違いです。
比喩(花・果実など)が少なくても、教育体系そのものは成立します。
ただし、現代の資格教育が目指すのは「限られた共同体の中で通じる教え方」ではなく、多数の学習者に、同じ基準で教え、同じ枠で採点できる技能です。その目的に対して、比喩(より正確には「参照物に基づく香味語彙」)が便利になりやすい、という整理になります。
現代教育は「答案として採点できる言語」を必要とします
WSETは英国のワイン・スピリッツ業界の教育需要に応えるため、1969年に設立された、と公式に説明しています。
この種の教育では、沈黙や「美味しい」だけでは評価できないため、観察内容を共通フォーマットで書けることが求められます。
その中核が SAT で、外観→香り→味わい→結論の順に、たとえば香りは強度、味わいは甘味・酸・タンニン・アルコール・ボディ・余韻などを段階尺度で記述します。
比喩は「必須」ではなく「共有を速める道具」です
重要なのは、WSETが「特定の花名を必ず書け」と要求しているわけではない点です。SATではディスクリプタは例示(indicative only)であり、毎回すべての項目に言及する必要はない、と説明されています。
つまり、比喩は本質ではなく、共有と訓練の効率を上げる手段です。
また、比喩は「同じ成分が入っている」という意味ではなく、印象を共有するための表現です(例:ペトロール香)。
「昔でもビジネスは成立した」ことと「現代教育で比喩が便利」は両立します
英国でワイン取引の歴史が長いことの象徴として、Vintners’ Company が1363年に最初の Royal Charter(勅許)を受けたことが挙げられます。
ただし当時の商取引は、同業者間で前提や文脈が共有されやすく、教育も徒弟的・現場的になりやすい一方、現代の資格教育は国・職種・経験の異なる多数を対象にします。
この環境では、香りを「果実・花・ハーブ・スパイス」などのカテゴリとして切り分け、構造(酸・アルコール等)と合わせて段階的に絞り込む、という“手順化”が有効になります。
「花名」を正しく結び付けられるかは、まず “正しさ”を何として定義するかで答えが変わります。
共有しやすい香りには「アンカー」が作りやすいものがあります
- ペトロール香:リースリング熟成で語られる kerosene/petrol 様の香りは、香気成分 TDN(1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene)が関与する、と研究で扱われています。
- バニラ:オーク由来の香りは複合的ですが、代表的なインパクト成分として vanillin が挙げられます(他の成分も寄与します)。
- 果実の例(簡単に):ソーヴィニヨン・ブラン等で語られるグレープフルーツ/パッションフルーツ系の香りは、揮発性チオール(3MH, 3MHA など)が主要因の一部として説明されます。
このように「原因物質の説明(化学的アンカー)」が比較的作りやすい領域では、多くの人で共有しやすくなります。
花名が難しいのは
花名の共有が難しいのは、スミレ(β-イオノン)やバラ(テルペン類)のように特定のインパクト化合物と結びつく例を除き、多くの場合、複数の微量成分が組み合わさった「複合的な印象」に過ぎず、1対1の同定が困難だからです。
また、マスカット系などアロマティック品種のフローラルさには、モノテルペン類(linalool, geraniol, nerol など)が関与する、と整理されます。
要するに、花名は「真理の同定」というより、方向性を短く伝えるラベルとして使われやすい、という性格があります。
誰が「正解」を決めるのか
絶対的な正解を決める一者は基本的にいません。代わりに、場面ごとに“正解の作り方”が違います。
- 同席のテーブル:正解を決める必要はありません。目的が共有なら「フローラル系」などで十分成立します。
- 教育(WSETなど):正解は「SATに沿って、採点可能な形で書けているか」です。WSETの資料では、見出し内のディスクリプタは indicative only(例示)で、すべてにコメントする必要はない旨が明記されています。
- 官能評価(研究・品質管理):訓練された評価者を選抜・訓練して運用する、という枠組みが標準化されています(ISO 8586等のガイドラインの射程)。この場合の「正解」は、参照標準でキャリブレーションしたパネルの合意です。
はい、花名を使った表現が無意味になったり過剰になったりするおそれはあります。
その主因は、「花名」が多くの場合、香りの原因物質と1対1で対応する“同定”の言葉ではなく、印象を共有するための便宜的なラベルだからです。
無意味・過剰になりやすい典型
- 花名を“同定”のように断定してしまう(「〇〇の香り=〇〇成分」だと言ってしまう)
- 花名だけが出て、構造(酸・甘味・渋味・アルコール感・ボディ・余韻など)が語られない
- 差別化や雰囲気づくりのために、具体語だけが細かくなる(情報が増えていないのに語彙だけ増える)
- 他人の発言に引っ張られて“合わせてしまう”(先に聞いた言葉が、香りの取り方に影響することがあります。)
この場合、花名は「伝達」より「演出」に寄りやすく、過剰表現になりがちです。
それでも花名が“完全に無意味”とは言い切れない条件
花名が情報として成り立つのは、「自由に好きな花名を言う」状態ではなく、同じ言葉を同じ意味で使うためのルール(運用)が用意されている場合です。
たとえば官能評価(品質管理や研究)では、評価者を選抜し、訓練とモニタリングを行って、用語選択のばらつきを抑えた「パネル」として運用します(ISO 8586 は、評価者の選抜・訓練・モニタリングの一般指針を示します)。
この発想では、語彙は「原因物質の同定」ではなく、比較・記録・再現性(少なくともパネル内の一致)を得るための道具になります。
つまり、花名は必須の正解ではなく、有益なら使う/不要なら使わないという位置づけです。
結論から言えば、ふだんの食卓でスワリングは必須ではありません。グラスに注いで静かに置くだけでも、ワインは空気と折り合いをつけながら、自分の速度で香りを立ち上げていきます。その自然な時間軸をそのまま受け取るのは、十分に合理的で贅沢な飲み方です。
それでもスワリングに意味があるとすれば、その役割は「香りの情報を、少し早く引き出す操作」です。グラスを回すと内壁に薄い膜ができて表面積が増え、揮発が進みます。同時に、ワインが空気を取り込みやすくなり、閉じ気味だった香りの輪郭が短時間で掴みやすくなります。軽いこもりや還元的なニュアンスがあるときに、印象がほどけることがあるのも、この“空気接触を増やす”作用によります(ただし、強い還元は空気だけで解決しない場合もあります)。
現代のワインテイスティング、とくにプロの現場でスワリングが推奨されやすいのは、限られた時間の中でそのワインの性格を素早く把握し、比較・評価に耐える形で「開いた状態」を確認する必要があるからです。そこには確かにビジネス上の効率性がありますが、同時に、同じ手順で条件を揃えるという標準化の目的もあります。要するにスワリングは、「より正しい味にする儀式」というより、情報取得を加速し、観察条件を整えるための道具です。
一方、食卓では目的が違います。回しすぎれば、香りの移ろいを飛ばして“ピークの断面”だけを先に見てしまったり、繊細さが早く抜けたりすることもあります。だから手順はシンプルで構いません。まずは回さずに香りを取り、十分に開いているならそのまま。閉じている、読み取りにくいと感じたときだけ、小さく1〜2回。この距離感が、ワインの個性を歪めずに楽しむうえで、いちばん誠実で実用的だと思います。
関連ページ
- posted : 2025-12-23, update : 2025-12-23
- Author : katabami (Editor) / ChatGPT (Writing Assistant)
- ワイン産地とぶどう品種の関係性はどのように生まれたのか « HOME » ワイン教育(WSETなど)における「Training(仕立て)+ Pruning(剪定)」の関係