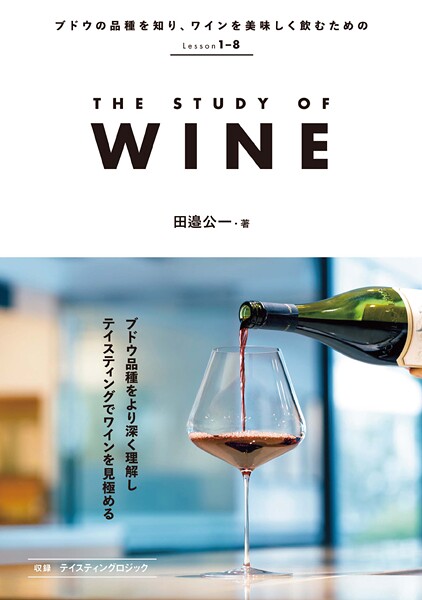フィロキセラ対策としてのぶどう台木導入と、その副産物
フィロキセラ禍への対策として「接ぎ木用の台木(rootstock)を用いる」という考えが生まれ導入へ至ったのは、北米で先に知られていた“葉コブの害虫”としてのフィロキセラの知識と、北米(特に東部)でヴィティス・ヴィニフェラがうまく育たない/長続きしないという経験知が、フランスでの大被害の原因究明と結び付いて、最終的に「根だけを抵抗性のある系統に置き換える」という設計に収束したためです。
北米での前提知識:フィロキセラは「葉コブの虫」として先に把握・記載されていた
北米の在来ブドウでは、フィロキセラは主として葉にコブ(葉コブ)を形成する形態が目につきやすく、昆虫学的にもこの症状を通じて把握されました。ニューヨーク州の州昆虫学者であった Asa Fitch は1855年にニューヨーク州で採取されたブドウの葉コブから本種を最初に記載し、当初はアブラムシ類の一種として Pemphigus vitifoliae(“grape leaf louse”)と命名しました。その後、分類学的整理が進み、現在では 学名 Daktulosphaira vitifoliae が一般に用いられています。
もう一つの北米側の経験知:ヴィニフェラが「なぜか」失敗しやすい
北米では、入植者がヴィニフェラ栽培を試みても、(当初は理由が明確でないまま)うまくいかない事例が繰り返されました。のちに昆虫学者 Charles Valentine Riley は東部北米で欧州ブドウが一貫して失敗しがちだった点をフィロキセラへの抵抗性欠如で説明し、北米の経験知をフランスの危機と理論的に接続しました。
フランスでの危機:見えていたのは「根の枯死」で、原因特定が難しかった
フランスで致命的だったのは、葉コブよりも地下で進行する根の加害(根の衰弱→枯死)でした。地下で起きるため、当初は「虫が原因か/弱った樹に後から付いた結果か」が争点になり得ました。
この段階で重要なのが植物・園芸学者であったプランション(Jules-Émile Planchon)です。1868年夏、ローヌ流域での被害調査のために組織された委員会(Gaston Bazille, Jules-Émile Planchon, Félix Sahut)は、ブドウの根に群がる微小昆虫の存在を確認しました。これを受けてプランションは本種を暫定的に Rhizaphis(「根のアブラムシ」)vastatrix と呼びました。ここで vastatrix はラテン語で「破壊するもの」「荒廃させるもの」を意味し、当時すでに観察されていたブドウ樹への深刻な被害状況を反映した命名であったと整理できます。
同年8月末には翅のある個体も採集され、送付標本の検討を経て、Victor Antoine Signoret(昆虫学者)が、コナラの虫こぶ害虫が属する Phylloxera との類似を根拠に Phylloxera の枠組みで捉える提案を行い、それを踏まえて呼称・分類が Phylloxera 側へ整理されていった(Phylloxera vastatrix という呼称が用いられた)――という流れで整理できます。
北米の「葉コブの虫」とフランスの「根の虫」が結び付く:同一種の別形態だと分かった
決定的だったのは、葉にいる形と根にいる形が同一種の別形態(多型)だと理解されたことです。この理解は、標本比較に加えて、翅型を含む生活史(どの形がどの形につながるか)の把握が進んだことで強まりました。1869年春にはフランスの動物・昆虫学者 Jules Lichtenstein が「フランスの地下型は、Fitch が北米で葉コブから記載した虫の地下型ではないか」という仮説を提示し、その後、フランス側でも葉コブが確認されて接続が強まりました。
Riley も北米側の標本・観察を背景に、米欧の個体の同一性や生活史理解を押し進め、解決策の方向性を強く後押ししました。
そこから「接ぎ木用台木」へ:解決策がこの形に収束する理由
ここまでが確定すると、対策は合理的に次へ収束します。
- 問題の核心は「ヴィニフェラの根がフィロキセラに弱い」こと。
- 一方で、フィロキセラが原産の北米では、在来ブドウ属の種が葉・根の攻撃に対して相対的に強い反応を示すことが多く、長期の共存(共進化を含む枠組み)で説明されることが多いと整理できます。
したがって、穂木(地上部)は従来どおりヴィニフェラ品種でワインの同一性を維持し、根(台木)だけを抵抗性のある北米系統に置き換えるという設計(接ぎ木+台木)が最も実装しやすい。
導入を遅らせた要因:対抗策の競合と「実装」の壁
接ぎ木+台木が有力だと分かっても、当初は次の要因が重なり、普及は段階的になりました。
- 薬剤派(“駆除”路線)と接ぎ木派(“再建”路線)の競合
- 初期には、硫化二炭素や硫化炭酸カリウムを根域に注入する化学的処理が実際に用いられました。
- また、1871年に国レベルの委員会が設けられ、1874年には「一般的な土壌で有効かつ経済的に適用できる方法」への高額懸賞も設定されるなど、当面は“駆除策”も真剣に模索されました。
- ただし被害拡大に対して効果・費用の面で限界が見え、化学処理派と米国台木・再植派の対立の末、後者が「不可避」に傾いていきます。
- 交雑派・自根で結実する“直産”路線への期待
- 直感的に、栽培者は最初から接ぎ木一本に賭けず、「アメリカ系統をそのまま(あるいは交雑で)自根で使い、接ぎ木を回避できないか」と期待しました。
- しかし、当時のフランス側の主流評価ではアメリカ系統のワインが望まれる品質像と合いにくい(いわゆる“フォクシー”と表現されることがある)という見方が強かったことや、そもそも“飲めるアメリカ品種”が“良い台木”とは限らず、試験で失敗が多かったことが、接ぎ木への収束を遅らせました。
- 土壌適応の壁:石灰によるクロロシス(鉄欠乏黄化)の理解が遅れた
- 初期の台木導入では、石灰質土壌での適応不良(クロロシス〔鉄欠乏黄化〕のリスクを含む)が大きな障害になりました。
- このため、「フィロキセラに強い」だけでなく「欧州の土壌条件(とくに石灰質)でも破綻しない」台木・組合せの確立まで、試験や(台木側の)交配・選抜が必要でした。
- 苗木供給・技術・商流のボトルネック(スケール問題)
- 実装には、台木選抜、台木×穂木の適合検討、接ぎ木・挿し木・大量増殖、販売・流通まで「栽培体系そのものの再発明」が要りました。
- しかも当初は、米国からの導入・同定・増殖・配布を支える商流が未整備で混乱があり、苗木の流通・移動をめぐる規制や管理も普及速度に影響しました。
- 加えて、資金面でも「抜根して再植」できるのは当初は富裕層に偏り、普及の速度を抑える要因になりました。
導入(普及)へ:1881年の“合意”と、その後の台木選抜・苗木供給
接ぎ木は果樹で古くからある技術でも、ブドウ畑の大規模再建には社会的・技術的なハードルがありました。それでも最終的に主流になった流れを象徴する出来事の一つとして、1881年ボルドーの国際フィロキセラ会議で、接ぎ木が「最も有効で経済的」と位置付けられたことがよく引用されます。ただし、これは“そこで突然決着した”というより、すでに有力化していた評価が公的に収束していく過程の節目として理解するのが自然です。
以後は、単に「米国ブドウを使う」ではなく、地域の土壌条件(乾燥、石灰など)に合わせて、北米種(例:berlandieri / riparia / rupestris)を基盤にした台木育種・選抜と、苗木生産・流通の整備が進み普及が加速しました。
結論から言うとフィロキセラ禍後の台木選抜は、①フィロキセラ耐性だけでなく、畑を再建する現実条件として ②挿し木で大量増殖できる(発根しやすい)、さらにフランスの多様な土壌条件に対応するため ③石灰質土壌への適応(黄化回避)を満たす必要がありました。
この3条件を同時に満たす“素材”が限られた結果、riparia と rupestris(増殖しやすい)+ berlandieri(石灰耐性)という役割分担で組み合わされ、今日の主流構造につながりました。もちろん地域・目的によって他種(例:V. amurensis 由来など)が使われる場面もありますが、歴史的な主流形成という意味ではこの3種が軸になりました。
まず実用になったのは riparia / rupestris:挿し木で増やせた
フランスの研究者が米国で多数の野生ブドウを採取しても、休眠枝からよく発根したのは V. riparia と V. rupestris が中心だったという整理が繰り返し示されています。
再建には苗木が大量に必要なので、ここが早期にこの2種(およびその交雑)が注目された最大の理由です。
しかし石灰質土壌で壁に当たる:石灰(高pH)と黄化の問題
V. riparia と V. rupestris だけでは石灰質土壌(高pH・炭酸カルシウム条件)での適応不良が大きな障害になりました。石灰質での栄養吸収(鉄など)に起因する黄化(chlorosis)は古典的産地に多い条件であり、台木選抜の別軸として早晩不可避になります。
そこで berlandieri:石灰耐性を補う“供与親”として重要化
この石灰適応の素材として重視されたのが V. berlandieri です。普及資料でも、berlandieri はテキサスの石灰地帯に自生し、高pH土壌に適応するが、挿し木発根が弱いので交雑で用いられると整理されています。
ここで歴史的に重要な人物が、テキサスで活動した米国のブドウ育種家・栽培家トーマス・ヴォルニー・マンソン(Thomas Volney Munson)です。マンソンはフランス側に、テキサス/ミズーリ由来の抵抗性素材(riparia、rupestris、berlandieri など)を提供し、フィロキセラ禍後の台木・交雑育種の方向づけに関わった人物としてまとめられます。彼はその貢献により1888年にフランス政府から農事功労章(Mérite Agricole)を授与されたと大学資料等に記載されています。
なぜ「3種の交雑」に収束したのか:berlandieri は“そのまま”では増やしにくい
berlandieri は石灰耐性の面で有力でも、休眠枝からの発根が弱く、純系のままでは苗木生産に乗りにくいため、実務上は riparia / rupestris(発根性)と交雑して使う方向に進みました。
結論から言うと、黄化がボトルネックになっていた品種・区画では、栽培は「楽になった(=安定した)」と言えることが多いです。ただし、品質が自動的に上がるとは限らず、台木の性質と栽培設計次第で結果が変わります。
栽培は楽になったのか
石灰誘導性クロロシスが出ていた区画では、石灰適応台木の導入によって、実務上「楽になった」に近い変化が起きやすいです。ここでの「楽」は万能化ではなく、主に事故率の低下/年変動の縮小を指します。
- 黄化による樹勢低下、欠株、成熟遅れの頻度が下がりやすい
- 収量・熟度のブレが小さくなりやすい
- 鉄資材(キレート等)や葉面散布など、救済的な対応への依存が相対的に下がりやすい(ただし完全に不要になるとは限りません)
一方で、石灰質土壌は水分条件や土層、排水の影響も強いので、黄化が抑えられても「別の難しさ」(乾燥ストレス、樹勢の出方、負荷設計など)が残ることはあります。
品質は向上したのか
品質については黄化が出ていた場合は「品質低下要因を除去できる」ので改善し得ますが、台木は樹勢・水分状態・養分吸収も動かすため自動的に向上するとは限りません。
- 改善し得る点
- 黄化が強いと果実の成熟(糖・フェノール)や香味の充実が頭打ちになりやすいので、黄化を抑える台木は「本来の成熟に乗せる」方向に働き得ます(この意味では「向上」というより回復・安定化に近いです)。
- 注意点(台木の副作用)
- 石灰耐性台木は同時に樹勢や水分ストレスの出方を変えるため、条件によっては樹勢過大(遮光・遅熟)、樹勢不足/水分ストレス過大(収量低下・成熟の偏り)が起き、品質が伸びない(下がる)こともあります。
したがって、石灰適応台木は「品質を上げる装置」というより、品質を落としていた原因(黄化)を取り除くことで、品質設計が成立する土台を作るものと整理するのが安全です。
石灰質土壌は「ベストではない」一方で、補う長所もあるのか
石灰質土壌が「ベストではない」というのは、自根のヴィティス・ヴィニフェラにとって鉄の利用性が下がり、品種によっては鉄欠乏黄化が起きやすいという意味です。黄化が強く出ると生育や結実が不安定になり、栽培上の大きな弱点になります。
ただし石灰質土壌には、黄化とは別に、条件次第で栽培上の利点になり得る性質もあります。たとえば、炭酸塩やカルシウムの存在が土壌構造(団粒性)や排水性に関係したり、有機物分解や窒素の利用性に影響したりして、区画によっては樹勢や水分状態を整えやすくなることがあります(ただし、土層・粘土量・水分条件に強く依存します)。
黄化が前面に出ている区画では、こうした利点を語る前に樹勢・生育が著しく損なわれます。石灰質に適応する台木は、黄化を抑えることで、石灰質土壌が持ち得る“別の利点”を、はじめて現実の栽培条件として活かせる状態に近づける、という意味を持ちます。
ありました。ただし「思いもかけなかった」の中身は、時代や立場によってズレます。ここでは実務的に、フィロキセラ対策として導入された台木が、のちに“別目的でも不可欠”と理解されていった効果として整理します。
「土壌・環境ストレスへの適応」を台木で設計できるようになった
台木は病害虫だけでなく土壌条件(=根が置かれる環境)への適応にも使えることが、のちに強く意識されるようになりました。
- 線虫など土壌害虫への抵抗性(フィロキセラ以外の“根の害”対策)
- 乾燥(干ばつ)への耐性・回復性の差(同じ穂木でも台木で反応が変わる)
- 塩分への耐性
- 石灰質土壌での黄化への耐性
「台木=害虫対策」という枠を超えて、区画ごとの土壌制約(乾燥・塩分・石灰・線虫など)を“台木選択の問題”として扱えるようになったことが、副次的に非常に大きい効果です。
樹勢・収量・成熟の“設計変数”として台木が組み込まれた
台木はブドウ樹の生理(吸水・養分吸収など)を変えるため、栽培者は台木を使って栄養成長と結実のバランスを調整できることを強く意識するようになります。
この発想は、フィロキセラ対策としての導入時点よりも、むしろその後の“台木の使い分け”が進む中で重要性が増した点だと思います。
「ヴィニフェラ品種を維持したまま」環境適応だけを変えられる、と理解された
接ぎ木では穂木(ヴィニフェラ品種)を保ちつつ、根の機能(抵抗性・耐性・吸収特性)を台木に担わせます。つまり、品種の同一性(=地上部)と、土壌適応(=地下部)を分離して設計できる、という考え方が実務上は非常に強力でした。
ただし「副次的な効果」には副作用も同居する
台木は万能薬ではなく、条件や組合せ次第で樹勢や水分ストレスの出方を変え、果実やワインの組成にも影響し得ます。
その意味で、台木導入は「思いもかけないメリット」だけでなく、台木選択という新しい難しさも同時に持ち込みました。
結論から言うと、品種の「国際品種」と同じ意味での“どこでも通用する万能台木”は、基本的にはありません。台木はワインスタイルよりも、フィロキセラに加えて 土壌・気候・病害虫(石灰=黄化、乾燥、塩分、線虫など)に合わせて選ぶ必要があり、地域差が大きいからです。
ただし、「世界の複数地域で繰り返し登場し、ナーセリーでも“定番枠”として扱われる台木はあるか」という意味なら、あります。代表例は次のように整理できます(=“国際台木っぽい”もの)。
暖地・乾燥寄りで広く出てくる定番
1103 Paulsen(1103P)/110 Richter(110R)/140 Ruggeri(140Ru)、そして地域によって Ramsey など。
例として南オーストラリアでは、最も一般的な台木として Ramsey、1103 Paulsen、101-14、140 Ruggeri が挙げられています。
また研究・技術文書でも、1103P/110R/140Ru は乾燥ストレス文脈で頻出の商業台木として扱われます。
冷涼〜温帯で「よく出てくる」定番
101-14 Mgt と 3309C は、北米の普及資料や講義資料で頻出で、地域の“定番台木”として扱われます。たとえば米国の普及資料では 3309C を「東部で人気」とし、別資料では「東部で最も推奨されることが多い」と整理されています。
ヨーロッパで“定番セット”になりやすいグループ
ヨーロッパでは国ごとの事情は大きいものの、ナーセリーの母樹園面積などを見ると、少数の台木に集中する傾向がはっきり出ます。
イタリアでは許可台木37のうち 1103P/Kober 5BB/SO4/110R/420A の5つで、ナーセリーの母樹園面積の約78%を占める、という整理が示されています。
スペインについても、資料によって表現は違いますが、少なくとも「母樹園面積」ベースで 110R と 161-49C が大きな比率を占める(Hidalgo 2002 の数値を引用)という報告があります。
なぜ「国際台木っぽい定番」が生まれるのか
万能台木が成立しにくい一方で、特定の台木が国境を越えて“定番”になりやすい理由は、概ね次の3点です。
- 1つ目は、適用できる条件の幅が比較的広いことです。土壌や気候の違いがあっても「多くの区画で大きく破綻しにくい」台木は、複数国で採用されやすくなります。
- 2つ目は、苗木として大量に供給しやすいことです。挿し木や接ぎ木の作業性が良く、歩留まりが安定し、流通量を確保しやすい台木は、ナーセリー側が生産計画を立てやすく、結果として市場に出回りやすくなります。
- 3つ目は、いったん普及すると切り替えにくくなることです。普及が進むにつれて、その台木を前提にした栽培指導や現場の経験が蓄積され、さらに母樹園や苗木供給体制もその台木中心に整備されます。その結果、合理性だけでは別の台木に移りにくくなり、定番としての地位が固定化します。
SO 4 はドイツでの選抜・実用化に時間がかかった台木です。実際、1920年代初頭からオッペンハイムで選抜が進み、1922年に最初の大増殖が行われ、1933年に承認された、という段階を踏んでいます。にもかかわらずフランスで中心的台木になったのは、「どこで生まれたか」よりも、フランスが大量再植を迫られた時期に、SO 4 が“量を確実に回せる台木”として供給・指導の仕組みに乗ったことが大きいです。
まず、SO 4 は現場的に使いやすい性格を持っています。挿し木・接ぎ木の作業性が良く、活着しやすく、植え付け後の立ち上がりが早い。こうした性格は、苗木生産側にとっては「大量に増やせる」「歩留まりが読みやすい」というメリットになり、栽培側にとっては「早く畑が形になり、収量回復が早い」というメリットになります。台木が“中心的”になるときは、適性の議論だけでなく、苗木として大量に回せるかが決定的に効きます。
次に、フランスで SO 4 が主流化した局面として、1950年代以降の再植・再建期(短期間に広い面積の植え替えが必要な局面)を外せません。この時期の現場は、理想的な区画最適化よりも、まず「確実に植えられ、早く生産に戻せる」選択に傾きやすい。そこに SO 4 の性格(増殖・活着・立ち上がりの強さ)が合致しました。
さらに重要なのが、供給網と技術指導の“標準化”です。ある台木が大規模に採用されると、母樹園(採穂園)・苗木業者の生産計画・現場の技術指導・栽培者の経験値が、その台木を前提に積み上がります。すると、次の植え替えでも同じ台木が選ばれやすくなり、結果として中心的地位が固定化します。つまり、SO 4 がフランスの中心的台木になったのは、能力だけでなく、供給と指導が SO 4 前提で回りはじめる「パス依存」が働いたからです。
まとめると、SO 4 はドイツでの選抜・承認までに時間を要した(1920年代初頭に選抜開始、1922年に大増殖、1933年に承認)にもかかわらず、いったん実用段階に入ると、増殖・活着・立ち上がりに強い性格が「再植需要が急増した1950年代以降のフランス」に非常に適合し、供給網と技術指導の標準化によって主流として固定化した――この流れで説明するのが最も自然です。
プランションばかりが取り上げられやすいのは、功績が単独で突出していたからというより、歴史の語りが「代表者」に収束しやすい条件を、彼が複数持っていたためです。
まず、プランションは1868年の初期調査で、枯死するブドウ樹の根にいる微小昆虫を確認した「三人の専門家」の一人として登場しやすく、物語の冒頭(原因究明の起点)に置きやすい人物です。
加えて、1874年に『Revue des deux Mondes』で大きな総説を出しており、「当時の知識をまとめた人」として後世の参照点になりやすい。そのうえ、この総説の中で「発見者」としての自己位置づけが強く、同僚への言及が薄いことが後年の研究で指摘されています。結果として、共同作業だった側面が要約の過程で薄まり、名前が前面に出やすくなります。
また、対策は薬剤・湛水など競合がありましたが、後世の叙述はどうしても「結局これが解決策だった(接ぎ木)」に収束します。そのとき、接ぎ木支持(いわゆる“アメリカ派”)の象徴として語りやすい人物がプランションで、こうした「勝った路線の代表者」効果も働きます。
さらにフランス(とくにモンペリエ)では、プランション像を固定する「記憶装置」(記念碑・彫像)があり、地域史・観光・教育の文脈で繰り返し再生産されやすい点も大きいです。
関連ページ
- posted : 2026-01-12
- Author : katabami (Editor) / ChatGPT (Writing Assistant)
- ラングドック・ルシヨンにおけるぶどう栽培の成立・拡大・単作化 « HOME » エノトリアは「ワインの土地」だったのか?